
設立2周年記念
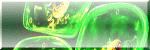
| 科学会案内(ガイド) |
| 入会案内 |
| 学術総会 |
| 学会誌 禁煙科学 |
| 認定講習会 |
| 禁煙支援士認定 |
| 教育医療施設 |
| 受賞・表彰 |
| お知らせ |
| トピックス |
| イベント等 |
| 週刊タバコの正体 |
| 子どもの禁煙研究会 |
| 禁煙治療研究会 |
| 国際交流委員会 |
| ダウンロード |
| リンク集 |
| 初級禁煙支援士名簿 |
| 中級禁煙支援士名簿 |
| 上級禁煙支援士名簿 |
■お悔やみ
日野原重明先生
お悔やみの言葉 高橋裕子
※日本禁煙科学会の発案者であり名誉顧問の日野原重明先生が7月18日午前6時半に105歳で逝去されました。心より衷心の意を表します。
■ふえる笑顔 禁煙ロゴ
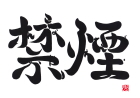 ※筋肉の疾患で体の不自由な浦上秀樹さん(埼玉県在住)が、口に筆を取って書いてくださった書画です。「けんこうなしゃかい ふえるえがお」でという文字を使って『禁煙』をかたどっています。
※筋肉の疾患で体の不自由な浦上秀樹さん(埼玉県在住)が、口に筆を取って書いてくださった書画です。「けんこうなしゃかい ふえるえがお」でという文字を使って『禁煙』をかたどっています。

■科学会ガイド(pdf)
※印刷用資料としてご利用下さい。
■科学会をネットで検索
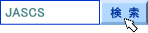
■禁煙科学(2007.11)
■禁煙支援資料(2013.03)
平成18年5月27日設立された日本禁煙科学会も、おかげさまでここに創立一周年を迎えることができました。皆さまのご支援・ご鞭撻に心より篤く御礼申し上げます。
創立一周年にあたっての吉田理事長のメッセージです。
平成19年(2007年)5月
日本禁煙科学会 事務局
禁煙科学の考え方
日本禁煙科学会理事長 吉田 修
(奈良県立医科大学学長)
タバコのないクリーンな環境と健康な社会を実現し、人類の福祉向上に貢献するにはいろいろなアプローチが必要である。医療従事者が日常の診療で患者の禁煙を支援するのも、子供たちに「その生涯を左右するような《喫煙という悪い習慣》を身に付けないように、というよりは《タバコ病に罹らない》ように」に教えるのも、或いは政治的に国の行政に働きかけるのも、いずれもわれわれの目的達成のために必要なアプローチである。そして、多くの人が自分にできるアプローチでそれぞれが理想とする《タバコのない社会》実現に向かって取り組んでいる。その取り組みにおいて不可欠のもの、基本となる存在が禁煙科学であると考えているが、その点について概説しておきたい。
「禁煙科学」はサイエンスとアートとヒュウマニティからなる
アメリカ近代医学発展の礎を築いたウイリアム・オスラーは、「医学はサイエンスとアートとヒュウマニティからなる」と教え、実践躬行した人である。オスラーの言葉の中の「医学」を「禁煙科学」に置き換えてみればわれわれが目指す「禁煙科学」になるといってもよい。
禁煙科学は Smoking Control Scienceである。Science・科学は体系的であり、実証が可能でなくてはならない。科学は狭義には自然科学を指すが、経済学・法学などの社会科学、心理学などの人間科学もサイエンスである。禁煙科学も自然科学のみでなく社会科学的要素も人間科学的要素含んだ幅広いものと考える。
ケンブリッジ大学の学長を務めたE.アシュビーは科学の社会的機能について「科学と反科学」の中で、「人類のおかれた現在の状況は、いくらかの科学者は科学の枠外にでて科学と社会の相互作用に働きかけるように求めている」と述べているが、現代は当時よりもさらに科学がもっと社会寄りになることを求めている。
2007年12月に京都で開かれた本学会の設立総会で特別講演をしたプルシャスカは「Population Treatment for Smoking Control」で、「Tobacco controlの中で禁煙治療は重要な部分を占めていないのはそれがpopulationをbaseにしたものではなかったからだ。すなわち喫煙者全てに適用できる方法がなかったからだ」と述べ、行動科学に基づいたTranstheoretical Modelを紹介し、その実績を発表した。これはまさに科学であり、それに基づいた治療はアートといえるまでに高めることができる。
ニコチン依存症、たばこ病の治療にはこのアートが必要である。最近の厚生労働省の実態調査で、2006年4月から医療保険の適用対象となったニコチン依存症の治療について、患者の約4割が治療後3ヶ月たっても禁煙をつづけられていることが明らかになった。関係者の多くは「ほぼ期待通りの効果」としている、はたしてこの程度の治療成績で禁煙支援、たばこ病治療がアートにまで高まったといえるであろうか?
人類の福祉を考え、無限の可能性を有する子供たちの未来を思うヒュウマニティ、思い遣りのこころが必要であることは申すまでもない。医療倫理、生命倫理の基礎的基盤になっているヒュウマニティ、禁煙科学はこの三者が統合された体系でなくてはならないといえる。
続きをみる

